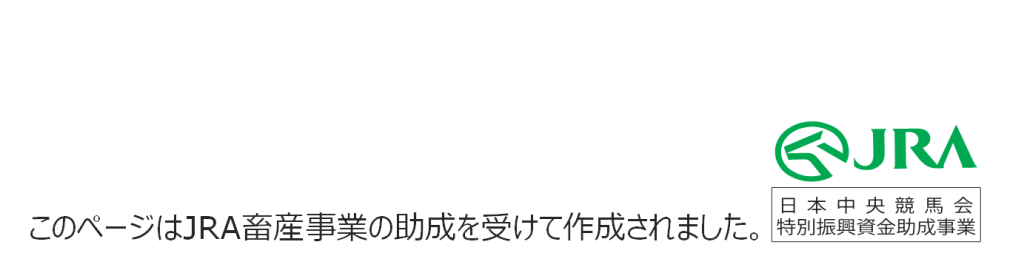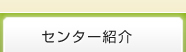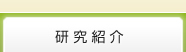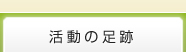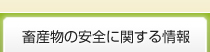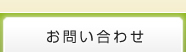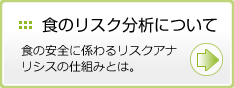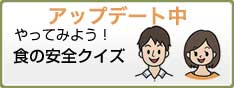お知らせ
第7回サイエンスカフェ「聞いてみよう!放射性物質と農産物のコト~福島の色々な食べものについて~」開催報告
掲載日: 2014年3月10日
福島の色々な食べものについて
1月17日、第7回サイエンスカフェ「聞いてみよう!放射性物質と農産物のコト~福島の色々な食べものについて~」を開催しました。
センター長の関崎勉教授のファシリテーションのもと、昨年5月までは福島県職員として農産物の対応に従事し現在は福島の農業復興に関する研究に取り組んでいる二瓶直登准教授による話題提供が行われました。
今回は様々な年代・職業の方が参加され、それぞれの視点からご質問やご意見をいただき、大変盛り上がりました。
※以下、記載がない場合の発言は二瓶氏
※質疑応答は一部抜粋
二瓶さんのこれまで
- 私の生まれは福島県のいわき市で、東北大学卒業後は福島県庁に入り、13年間農業試験場で大豆や麦の栽培法について研究をしていました。また、社会人ドクターという制度を使って東京大学に通い、有機農業についての研究も行いました。
- 震災の日は試験場に居ました。4月からは県庁に転勤することになっていたのですが、全体の人事異動が遅れ、震災後は主に農業に関する文献収集を行っていました。6月に県庁に異動し、食品安全に関する課に入り、放射性物質の検査データを取りまとめていました。業務として最も大きかったのは、県民の方からの電話相談です。最大では合計で8時間も話し続けたことがあります。
福島県の農業について
- 福島県は農業が大きな産業となっており、コメ、キュウリ、トマト、モモ、ナシなどが多く生産されています。今日覚えて帰ってもらいたいのが「天のつぶ」という福島県が作った新品種のコメです。震災で発売が少し遅れてしまいましたが、とても美味しいので、是非食べてもらいたいです。
放射性物質の作物汚染
- 放射性物質の作物への影響には、直接汚染と間接汚染の二通りがあります。放射性物質が直接実や花に付くのが直接汚染で、事故直後に問題となりました。それに対して、土壌中の放射性物質が根を通して植物体内に入るのが間接汚染です。
- 原発事故後、降下してきた放射性物質は、植物や土壌を均一に汚染するのではなく、ぽつぽつと不均一に汚染することが分かりました。
福島県で行われている検査の取り組み
- 福島県では様々な方面から検査の取り組みをしています。まず生産段階で農産物をモニタリング検査します。それから、実際にスーパーに並んでいるものを購入して検査し、本当に基準値を下回っているかの確認もします。学校給食についても検査しています。検査の数として多いのは家庭菜園で作ったものです。各公民館に一台ずつ検査機器を入れて、作物を持参すれば計測できるようになっています。また、家庭で実際に作った献立を検査する陰膳検査もしています。
- モニタリング検査は基本的には県内59の市町村単位でやっています。作物ごとにサンプルをとって、その値が基準値以下であれば流通できます。基準値を超えた場合は、市町村単位で出荷制限がかかります。
- 基準値の約10倍の値が出た場合は、出荷制限の上の収穫制限になります。出荷制限と収穫制限の間には摂取制限があります。
- 検査をする際には、サンプルは細かく刻みます。ナイフは使い回しをせず、使い捨てにしています。福島県の農業総合センターにはゲルマニウム半導体検出器は現在10台あります。1台2,000万円ほどします。1トンから2トンもの重さがあるので、床がしっかりしたところにしか置けません。空気や水等、環境検査用のものも含めると全てで30台弱あると思います。
参加者
基準値を超えて出荷制限になった場合、生産者には補償がありますか?
二瓶
東電に対して賠償請求されます。例えば、福島市の梅がまだ出荷制限となっていますが、県や国が出荷してはならないと言っているので、生産者には補償があります。お金が関わってくるので、モニタリングの値は重要です。
関崎
出荷制限、摂取制限、収穫制限はどのように違いますか?
二瓶
出荷制限は販売することはできないけれど、収穫して自分の責任で食べるのは構いません。さらに値が高くなると、収穫しないでください、食べないでください、となります。
参加者
摂取制限は基準値の何倍だと出されますか?
二瓶
私も何度も厚生労働省に問い合わせたことがありますが、明確な基準はありません。例を見ていると、大体5倍などで摂取制限になっています。高い値がどのくらいの量出たのか、どの地域か等、総合的な判断をしていると思います。
参加者
出荷できなかった農作物は今どこにありますか?
二瓶
コメに関しては基準値の100ベクレルを超えたものは焼却処分が基本となっていますが、その他の作物については、私が県庁にいた時は埋めるしか方法がなく、非常に問題になっていました。
検査データの傾向
- 平成25年11月までに、約450品目、約103,000点(コメ以外)をモニタリング検査しています。
- 今回の原発事故で問題になった放射性物質は放射性セシウムと放射性ヨウ素です。ストロンチウムは少ししか検出されませんでしたし、また、分析に時間がかかるので、放射性セシウムと放射性ヨウ素の値が低ければストロンチウムも低いだろうと推測することになっています。
- 放射性ヨウ素は半減期が8日と短く、事故直後には直接汚染としてホウレンソウ等で検出されましたが、その後は段々と減っていきました。
- コメ以外の穀類について見てみると、2011年6月頃は2,400ベクレル/kgのクリ(クリは食品衛生法上は穀類に分類される)や630ベクレル/kgのコムギが出て、出荷制限となりましたが、一年後の値は低くなりました。これは放射性物質の物理的半減期という性質と、除染をしたからです。
- 除染は土壌の表面をはぎ取れればもちろんそれが良いのですが、その土壌をどこに置くのかという問題があります。そのため、濃度が高い地域ははぎ取りをし、そこまで高くない地域では、表面とその下の土壌を混ぜ合わせる反転耕を行っていました。
- 穀類も平成25年になり濃度は低くなりましたが、ダイズは高い濃度が検出されやすく、その原因や対策について、今私は研究しています。
- 野菜は事故直後に起こる直接汚染の影響が大きく、最大のものだと84,000ベクレル/kgのクキタチナが出ました。穀類と同様に値は低くなっていき、去年の8月からは100ベクレルを超える野菜はほとんどありません。
- 果樹では、事故当時まだ花も咲いていませんでしたが、ウメで高い値が出ました。表皮からの取り込みがあったためです。表皮を水で洗い流す・剥ぐという対策をし、一年後にはだいぶ値が低くなりました。
- 福島県は浜通り、中通り、会津地方の三つの地域に分けられます。やはり原発に最も近かった浜通りで生産された作物で最も多く検出されました。事故から一年後、浜通りの野菜・果実は、100ベクレルを超えるものも少しありますが、検出限界以下が80%以上となりました。原発から最も遠い会津地方では、事故直後は少し検出されましたが、現在はほとんど検出されていません。
林産物と水産物はまだ注意が必要
- 野菜・果実、穀類、畜産物は落ち着いてきましたが、まだ注意しているのは林産物と水産物です。事故直後のきのこや山菜はびっくりするほど高濃度のものがありました。二年目も100ベクレルを超えるものが出ています。その原因は、単純に林産物は吸う能力、蓄積する能力が高い等だといわれています。ただ、出荷制限はきちんとかかっているので、店頭に福島県産のきのこが販売されていれば、それは検出されていない地域で生産されたものです。
- きのこは人工的に原木や菌床で栽培されるものについては、だいぶ値は低くなりました。福島県は多くの原木を生産していましたが、原木の基準が非常に厳しく、食品よりも低い50ベクレル/kgとなっています。
- 水産物では、最も高濃度で、18,000ベクレル/kgのヤマメが出ました。調査のためにわざと濃度が高そうなものを獲っているということもあるかもしれませんが、今でも高濃度のものが出ています。ただし、水産物でも、人工的に餌を管理できる養殖魚は大丈夫です。また、品種によって値は大きく異なります。貝類や海の上の方にいるシラスなどではほとんど検出されていません。こういうものについては試験操業という形で少しずつ獲り始めています。それに対して海の底にいるカレイやマダラはまだたまに高濃度のものが出ています。
関崎
今は原木や菌床は福島県以外から持ってきているのですか?
二瓶
基準を下回っているものを使っているか、輸入をしたり、他の地域のものを使っているかもしれないですね。
参加者
淡水魚と海水魚ではセシウムを排出する機能が違うのですか?
二瓶
海水魚は塩分濃度の高いところで生活するので放射性セシウムを出す機能が高いのに対して、淡水魚は逆に取り込む機能が高いので、淡水魚の方が高濃度が出やすいそうです。
関崎
私たちの体は食塩でいうと0.8%の塩分濃度になっていて、海水魚も大体同じくらいです。海水はその4倍くらいの濃度です。海水魚は体内の塩分濃度を一定に保つため、入ってきた塩をどんどん排出する機能が高く、放射性セシウムも一緒に出ています。それに対して淡水魚はむしろ体内の塩分を出さないようにしなければなりません。そうした違いがあります。
参加者
資料では2012年3月までのデータしか出ていませんが、聞いた話では、2011年から2012年までは概ね値は1/3になり、2012年から2013年でまた1/3になったので、値は相当減ったということです。
二瓶
それは事実だと思います。今問題なのは、林産物と水産物というように、ターゲットが決まってきました。
コメの「全量全袋検査」が始まるまで
- 福島県はコメの生産量全国4位(事故前。事故後は7位)、生産量は36万トン、30kg袋にすると1,200万袋あります。
- 事故後、野菜等では特に作付制限がありませんでしたが、コメは主食で生産量も多いため、県が積極的に介入し、土壌が5,000ベクレル/kgを超えるところでは作付制限をしました。自主的に作付しなかったところもあり、合計8,500ヘクタールで作付けされませんでした。作付面積の11%に当たります。
- コメの検出の傾向を見るという目的で、まず全体的に粗く予備調査を行いました。予備調査で値が高かったところをより細かくサンプリングし、本調査では全部で1,700点検査しました。本調査の結果、全てが当時の暫定規制値500ベクレル/kg以下だったので、県知事が安全宣言を出しました。しかし、その後の自主検査で500ベクレルを超えるものが見つかりました。緊急調査として追加で33,000点調べた結果、自然乾燥だとより値が高くなる等、大まかな傾向が分かりました。
- 平成24年度は抽出検査ではなく、収穫したものを全て検査しようということになりました。前年度に安全宣言を出した後に高い値のものが出てしまったので、同様のことがまた起こってしまうと福島県のコメはもう売れなくなってしまうのではないかという思いがあったためです。
- 全量全袋検査を行うに当たり一番問題だったのは検査機器です。ゲルマニウム半導体検出器では一点30分くらいかかり、それを県で10台保有していて、一日10時間動かせるとすると、一日200点が最大となります。1,200万袋だと50,000日かかってしまいます。農家はやはり年内に新米として出したいので、10月11月12月の三ヶ月が勝負です。その間に1,200万袋を検査できるベルトコンベアー式の機器を作らなくてはなりません。
- 「こういう機器が欲しい」と仕様書を作り、各メーカーにお願いをしたところ、島津製作所、三菱、キャンベラ、富士電気、日立の5社が手を挙げました。今は200台が福島県に入り、1分間に2,3袋検査をしています。
参加者
どこの機器が良かったのですか?
二瓶
それぞれに特徴があります。島津は高性能ですが、とても繊細でケアをきちんとしないとなりません。三菱と日立は、ベルトコンベアー上を流れていくとフタが閉まるようになっていて外部を遮断するので、線量が高いところでも検査できるというのが売りです。キャンベラはアメリカのメーカーで、頑丈です。アメリカの会社が面白いと思ったのは、試作機を作るときに「県が買う」という契約をしないと作れないということです。富士電機は最初に試作機を作ってくれて安く、色々とオプションを付けてくれました。日立のものは最初売れなくて県庁もどうしようかとなったのですが、機器をトラックに積んで各農協を回って売り込みにかかっていました。最終的には同じ数くらい売れました。一台2,000万くらいで、全て国からの基金からお金が出ます。
関崎
機器は農協が買っているのですか?
二瓶
市町村ごとに地域協議会とうものがあり、その中心となっているのが市町村の役員や農協なので、農協に売り込みにいったようです。
参加者
市町村によって使う機器が違うのですね。
二瓶
そうです。最初は県が一括で購入して市町村に配るという案もありましたが、やはり使う人に選んでもらった方が良いということで、お金だけ分配して購入してもらうことになりました。
参加者
福島県ではそんなに検査をしていても、周りの県ではチェックせずに出荷しているということが気になるのですが。
二瓶
確かに県境で対応が変わるということは気になりますが、福島県が隣の県にやりなさいと言うことはできません。国であれば言えるのですが。
コメの全量全袋検査の流れ
- まず農家が自分で米袋に生産者バーコードのシールを貼って、検査所に持って行きます。30ベクレルか40ベクレルを知るためにはゲルマニウム半導体検出器を使わなくてはなりませんが、開発したこの検査機器は基準値である100ベクレルを超えるか超えないかを知るための機械なので、モニターには○か×で結果が出ます。○であれば、検査済ラベルのシールが貼られます。ここまでが玄米の状態です。
- その後精米をしたものについては、安全性が確認された玄米を原料とした精米として、検査済ラベルのシールが貼られます。精米からは個別のデータを追えなくなっているのですが、検査して基準を満たしているということは分かります。私が最後に担当した仕事がこのシールのデザインでした。シールがコピーされるのを防ぐために色々な工夫をしてあります。
- 平成24年度の全量全袋検査の結果は、1,200万袋中、100ベクレルを超えたものが71袋でした。今年は現段階で28袋です。カリウム施肥をきちんとしているほ場で出たものもあるので、きちんと要因の解析をしなければなりません。
関崎
検査機器のモニターには○か×で出るということですが、機器の精度も勘案されているのですか?
二瓶
されています。基準値は100ベクレルですが、全量全袋用のこちらの検査機器は多少精度が粗いので、スクリーニングレベルとして70~80ベクレルを設定しています。スクリーニングレベルは機械ごとに決まっています。スクリーニングレベルを超えたら、県にコメを送り、ゲルマニウム半導体検出器で再度検査を行います。
参加者
福島県で聞いた話ですが、福島県産と書くと売れないので、国産米と書いているとのことですが、本当ですか?
二瓶
そういうことは多いと思います。先ほどのシールのために1,000万枚の予算を取りましたが、実際には600万枚くらいしか使われませんでした。残りの400万枚分のコメについては、国産米と表記したりして、レストラン等に売られました。買う方もどうせ賠償があるから良いだろうと安く買うという悪循環があります。賠償されるので安く買われても手取りは同じですが、農家のプライドとして「そういう問題じゃない」と思う人もいます。
関崎
牛肉でも同じようなことがあり、霜降りの良い肉でも福島県産と書くと買ってもらえないのではないかと流通側が国産牛と書き安く売られているようです。
参加者
玄米を精米するとどのくらい濃度は変わるのですか?
二瓶
放射性セシウムはコメの表皮に多いので、精米すると3分の1くらいにはなります。
参加者
検査済ラベルをたどれば、基準値以下であることだけでなく、何ベクレルであったか分かるようになっているのですか?
二瓶
個別番号が記載されているのは玄米用の検査済ラベルで、精米用の検査済ラベルにはそうした情報は盛り込まれていません。盛り込もうと色々試行錯誤してみましたが、今はそこまでできていません。
参加者
福島県でほ場が汚染された時に、これを機会に減反しようという話にはならなかったのですか?
二瓶
自主的に放棄した人が多く、これを機会に・・という雰囲気ではありませんでした。簡単に農村が崩壊してしまうような感じだったので、それよりも、どう残そうかという話になっています。
参加者
コメは一年ごとに考えれば良いけれど、魚は何年も生きるので、収穫がずっとできないという状態になってしまうのですか。
関崎
魚の中にもずっと放射性物質があるわけではなく、出たり入ったりしています。初期の頃は海の上の方に放射性物質があったのでシラスなどが問題になりましたが、段々と下に下がっていきました。海底の上のあたりに生育しているゴカイなどの生物に取り込まれて、それを食べるヒラメ等に入り問題になっています。段々と問題となる場所が変わっていっているので、ずっとということではないと思います。
二瓶
水産物も全量検査ができれば良いのですが、難しさがあります。検査をする際には、重さと大きさが均一であることがポイントになっています。コメは30kgと重さが均一ですが、魚はバラバラです。全量検査は、機器の問題と厚生労働省の認可の問題があって、現在全量検査が認められているのはコメと干し柿だけです。干し柿は干しているために値が高くなりやすく、なかなか出荷できていませんでしたが、コメの検査機器を少し改良した機器を作り、現在は全てを検査して出荷するようになっています。コメと干し柿の他はゲルマニウム半導体検出器で計測しなければならないことになっています。
参加者
検査機器の正確さという問題はあるかもしれませんが、地域で砂場の砂を計測した時に去年のものより今年の方が高かったということがありました。なぜこういうことがあるのでしょうか?
二瓶
それは新しく降ってきたということではなく、不均一性だと思います。私が研究に使っているほ場でも、取る場所によって濃度が倍くらい違うことがあります。今でも新しく出ている放射性物質はゼロではないけれど、土の濃度を高めるほどの量ではありません。